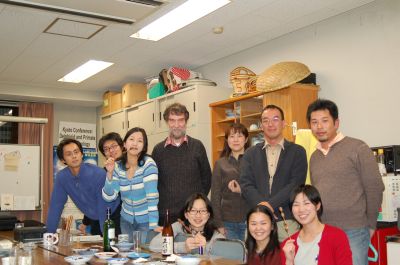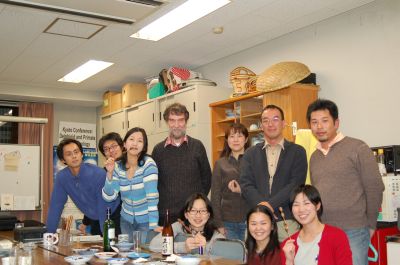第2回虫たべっ会
虫はたべもの−ラオスの昆虫食文化−
2006年3月29日(水)@京都大学理学研究科人類進化論研究室
参加者13名
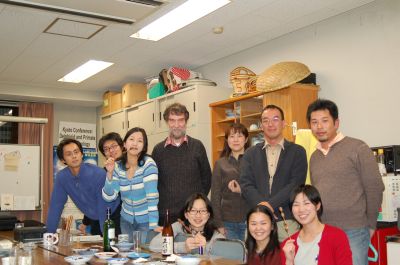
始めに、V.B. Meyer-Rochow氏(Bremen Univ.,and Oulu Univ.,浜松医科大学客員教授)に昆虫民族学の話をしていただいた。
Why do not eat insects?
- 食糧としての昆虫
- パプアニューギニア、オーストラリアなどを中心に食べられる昆虫の種類概観
- 薬としての昆虫
- 効用あれこれ
- 装飾・鑑賞のための昆虫
- 髪飾り
- 虫のデザインを使って
- 娯楽のための昆虫
- 楽器としての利用
- 戦かわせて遊ぶ
- 指標としての昆虫
- 健康状態をシラミで把握
- 法医学における昆虫
- 神話・伝説・歌・踊りにおける昆虫
- いい伝えなど
参考資料:V.B.Meyer-Rochow (1982) 「昆虫と民族学ー昆虫のいろいろな利用」インセクタリウム(19): 18-23.
次に野中健一さんに、ラオスの昆虫食の紹介をしていただいた。
次に試食をした。

材料はラオス産カメムシ、ケラ、バッタ、イナゴ、セミ2種、フン虫、など


やはり見た目も大事なのでしょう。市場ではこのような形で売られているそうです(右のようにバラ売りもあるのでしょうが)。カメムシ特有の臭みは不快なものではなく、何かの香辛料のような、スパイシーであるのに、どこかやわらかい味わいが口に広がります。
個体によって苦味がきついものがあるらしく、食べる人によって好き嫌いは別れました。私は苦い”ハズレ”カメムシにあたることがなかったですが、それは苦いのを苦いと感じていなかったのか、本当に”苦い”カメムシを引き当てていないのかは不明です。野中氏はラオスで生カメムシ食べを経験され、食べた後はお花畑が広がるような爽快な感覚だったそうです。今回お花畑が広がった人はいなかったようですが、カメムシの臭みを料理のスパイスとして使う国もあるというのはなんとなくわかりました。

今回の虫のなかでもっとも人気があったのが、このフン虫です。フンコロガシですよ、これ。フンコロガシという名のせいか参加者は若干食べるのを躊躇していましたが、ところがどっこいとっても美味しいのです!ナッツのようで、カリっとした歯ごたえ。自分が頑なに拒んでいたことはなんだったんだ・・・、本当にフンにまみれて生きているのですかー? 美味しいというコメントしかでてきませんでした。
フン虫の株はあがったようです。

2種類のセミを食べました。翅はむしられていました。冷凍物だったせいか水っぽかったので、レンジで加熱すると食べやすくなりました。屋久島にいるときに私はセミを捕まえては七輪で塩焼きにして食べていたので、その味のよさには自身があったのですが、フン虫の美味しさにおされていました。なので、新鮮なセミを食べてほしいなぁと思いました。オスとメスでは身体の筋肉のつき方が異なるのですが(オスは鳴くので筋肉が多い)、それを比較しながら食べるのを忘れていました。

これは昆虫食の王道といってもいいでしょう。初心者向けです。誰もが抵抗なくパクパク食べていました。シャクシャク感(サクサクではない)、後味のよさ、食草の影響かどこか爽快な味わいもあります。参加者の松原さんの差し入れの子エビと並べてもなんら劣ることのない、食べ物です。
参加者の角川さんにいただいた日本酒と赤ワインを飲みながらつまみにします。がつがつ大量に食べるものではないです、チビチビ酒を飲みながら食べるには虫は最適だということがわかりました。嗜好品ですね、これは。

みな、並んだ虫に興味津々です。
参加者にとったアンケートの結果、全員が美味しいと答えていました。これは第1回の結果と同様です。今回も参加者のほとんどが幼少期に虫を食べた経験があったため、参加している人にすでに偏りがありますが、味さえよければ虫は十分利用可能な食材であることをより強く実感しました。カメムシは人により好き嫌いが別れましたが、やみつきになりそうな感じがありました。ラオスでは結構な値段で取引されているそうで、そういった”大人の味”が付加価値をつけているのかもしれません。前回のオオスズメバチのように単価が高いものはないですが、日本では簡単に入手できるかどうかが不明なので、今後参加者に利用されるかどうかは入手しやすさに影響されるであろうと思います。
今回はあまり調理をしなかったが、たくさんの種類があったため、味を食べ比べるという楽しみがありました。よって、今回はそれぞれ虫を食べながらその感想を話合うという形になりました。現地で加工する段階で塩やその他の調味料たくさん使っているので、小さい虫ほど虫本来の味が少なかった。ケラやバッタなどは甲虫に比べてキチン質がうすいため、カリカリ感はあまりなかったが、虫の中身が噛むと同時にじわっと口の中に広がってくる。それはある人に言わせると「虫味」でまずいといわれてしまうかもしれない。
見た目がきつい、という感想もあったが、私はその領域を乗り越えているらしく、まだ食べたことのなかった水性昆虫を見て「絶対あれを食べるぞ」と心に決めていた。ひとつしかなかったので、争いが生じるだろうと心配していたけれど、みなあっさりと「どうぞ!」とおっしゃってくださったので、遠慮なく食べました。私しか食べていないので、感想を述べる義務があると思いますからここで挙げておきます。今回の虫のなかでは一番くせがなく、しかも大きめで食べ応えがあって、文句のつけどころがありません。
マイフェイバリット昆虫の仲間入りです。
(ちなみにマイフェイバリット昆虫はアオバハゴロモとカミキリムシの幼虫です)
今回も”採る”ところから始めることができなかったので、少し物足りなさが残りますが、虫の食べ比べをすることができ、虫の味の違いを体験することができたのは参加者の皆様には評判だったようです。これはきっと今後虫を採るときに、どの虫を食べるのにどれに労力をかけるかという判断において基準になると思います。私だったらまっさきに水性昆虫を採りにいきます。
参加者みなさんは何を採りにいくでしょうか。
特別ゲストのマイヤーロホウ氏のおかげで、とても有意義な議論をすることができました。特に食べる側の味覚のレセプターの違いによって、民族間の食べる昆虫の種類に違いが生じる可能性があるという仮説は、眼からうろこです。マイヤーロホウ氏や野中氏の人間の昆虫民族学に対し、霊長類の昆虫民族学を広げて生きたいという野心も駆り立てられました。
前回と同様になんだか身体の内側が熱いです、鼻血が出そうな感じもあります。第3回開催が待ち遠しいです。参加者のみなさま、ご協力ありがとうございました。
参加希望の方は、こちらまでご連絡ください。
戻る