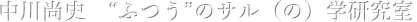ニュース
解説:Shimooka, Y., Nakagawa, N.: Functions of an unreported "embrace" gesture between female Japanese Macaques (Macaca fuscata) in Kinkazan Island, Japan. Primates, 2014, 55: 327-335.
(要旨)
本稿の英文サマリーを中川が和訳したものを以下にしるす。
近年、複数の感覚信号の同時生起の効果、有効性、意味についての研究が盛んである。われわれは、金華山に生息する野生ニホンザルにおいて、リップスマッキングという表情を必ず伴い、時にガーニーという音声も伴うこれまで報告のなかった「対面で向き合って抱き合い体を前後に揺する身振り」を観察した。本研究では、その機能を明らかにする目的で、その型や生起する文脈を調べた。22日間183時間の観察中に88事例の「体揺すり抱擁」を記録し、すべての事例にオトナメスが関与していた。オトナメス同士で行われたうち71事例について、その直前の行動を調べたところ、グルーミングの中断13事例、攻撃11事例、接近42事例で、接近のほとんどは血縁関係にはないグルーミング相手であった。また、直後はほとんどグルーミングに移行した。こうしたことから「体揺すり抱擁」はストレスフルな状況で生じ、そうした緊張を緩和する機能があるのかもしれない。こうした機能は、リップスマッキングとガーニーについて報告されている文脈や機能と一致する。リップスマッキングとガーニーと対照的に、非発情メス間での「体揺すり抱擁」も(体揺すりを伴わない)対面抱擁も報告がない。しかしながら、他のマカク種では、(体揺すりを伴わない)対面抱擁は敵対的交渉後に起こる親和的行動としてしばしば観察されており、和解行動、あるいは接近直後に起きた時は挨拶の機能があるとされている。金華山の「体揺すり抱擁」は、生起する文脈としても機能としても、ニホンザルでは"隠れていた"(体揺すりを伴わない)対面抱擁という古い身振りや、ニホンザルでも観察されているリップスマッキングという古いディスプレイと類似しているといえる。触覚信号としての対面抱擁は、祖型のマカクにおけるリップスマッキングという視覚信号と機能が重複したために、"隠れた"のかもしれない。
(解説)
この行動には個人的にたいへんな思い入れがある。1984年10月、私は修士課程1年の大学院生として金華山でニホンザルの採食生態学的研究を開始しましたが、そこで観察するうちにこの奇妙な行動が目に飛び込んできました。オトナメス同士が抱き合って座り、出会いの挨拶を交わすがごどく互いの腕を相手の体に回して抱き合った状態で、体を前後に揺する。唇を突き出し気味にして小刻みに開閉する「リップスマッキング」という表情と、「グニュグニュグニュ」と聞こえる「ガーニー」という音声を伴っている。それまでごく短期間ながら嵐山(京都府)、高崎山(大分県)、幸島(宮崎県)、屋久島(鹿児島県)でサルの観察をしてきたが、こんな行動は見たこともなかったし、聞いたこともなかった。金華山の長期継続調査を率いる伊沢紘生先生に尋ねたところ、下北半島(青森県)と白山(石川県)のサルではやるとのことだったが、金華山でさえ頻繁には見られないので、ともかく見たら記録することにして、とりためていつかまとめようと思っていた。
それから13年の歳月が流れた1997年10月、大学院の後輩にあたる下岡ゆき子さんが、やはり修士課程1年の大学院生として金華山に行き、この行動を「ハグハグ」と名づけて(ちなみに、私は「抱き合い体揺すり、Embrace & Rockingと、伊沢先生は「ユサユサ」と呼んでいた)、その機能を探るべく調査を開始し、結果を修士論文にまとめた。しかし、学会発表はなされたものの出版されることはなく時が流れた。そこからさらに8年が経過した2005年9月、下岡さんも含め大勢の研究者の協力を得て、屋久島で性行動の調査を始めた時、やらないと聞いていた抱擁行動を屋久島のサルがやるのを初めてみて、抱擁行動の地域間比較研究(Nakagawa et al., 2015)を急遽始めたのだが、先行し非常に面白い結果の出ている金華山をぜひ独立した論文としてまとめるべきだと思い、下岡さんの修士論文をベースに私がトレンドを取り入れるべく複数の感覚信号の話題として扱ったり、系統発生の議論を加えたりといった味付けを加えて投稿論文に仕上げ、なんとか掲載にまで持っていった。投稿前から一番不安視していたのが、緊張緩和の機能を主張するにも関わらず、ストレスホルモンやストレスの行動指標であるセルフスクラッチなどの自己指向性行動のデータがないことであった。下岡さんが修士論文を書いた当時はまだそれほど周知されていなかったので当時としては問題なかったが、いまは当然のようにこうしたデータを収集するからである。そしてやはり案の定査読者に要求されたが、なんとか目を瞑ってもらえたという経緯がある。われわれの分野の研究は、古びてしまうスピードは遅いが、それでもやはり収集したデータは早めに出版しないといけないことを痛感する経験であった。